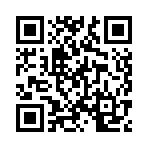2022年03月18日
海神社
なぜ、内陸部に海神社があるのか、以前から気になっていたので、行ってみた。


ここのご神体は、豊玉彦命、国津姫命で現在の熊野市から召喚したので、「海神社」となったようだ。知らんけど。
西暦800年代に建てられたそうだが、ここは根来寺の続きになっていて、豊臣秀吉の紀州攻めの時に、全て焼き払われたそうである。
なんと、令和2年に社務所を新築していた。


寄付一覧の石碑には、知ってる名前がたくさんあった。地域では、「ウナガミさん」と呼ばれているようである。知らんけど。
日曜日は、粉河チャペルへどうぞ。
ここのご神体は、豊玉彦命、国津姫命で現在の熊野市から召喚したので、「海神社」となったようだ。知らんけど。
西暦800年代に建てられたそうだが、ここは根来寺の続きになっていて、豊臣秀吉の紀州攻めの時に、全て焼き払われたそうである。
なんと、令和2年に社務所を新築していた。
寄付一覧の石碑には、知ってる名前がたくさんあった。地域では、「ウナガミさん」と呼ばれているようである。知らんけど。
日曜日は、粉河チャペルへどうぞ。
Posted by ちゃーちゃん at
18:10
│Comments(2)
2022年03月18日
桜池
先日、久しぶりに桜池へ行ってきました。


昔、紀州藩は55万5千石と言われていたが、徳川頼宣が紀州に入ったときは、そんなに石高はなかった。
頼宣の命でこの池は造られ、粉河、打田の田畑330へクタールが潤い、江戸後期に大畑才三が小田井を造ってやっと55万石になったとか。知らんけど。
その池が今や、バスフィッシングのメッカとなっている。

近隣の小学生の遠足地となっている。

日曜日は、粉河チャペルへどうぞ。
昔、紀州藩は55万5千石と言われていたが、徳川頼宣が紀州に入ったときは、そんなに石高はなかった。
頼宣の命でこの池は造られ、粉河、打田の田畑330へクタールが潤い、江戸後期に大畑才三が小田井を造ってやっと55万石になったとか。知らんけど。
その池が今や、バスフィッシングのメッカとなっている。
近隣の小学生の遠足地となっている。
日曜日は、粉河チャペルへどうぞ。
Posted by ちゃーちゃん at
07:15
│Comments(0)